大阪万博の開催に合わせて、京都国立博物館、奈良国立博物館と同時に、大阪市立美術館でも展覧会を開催している。
大阪市立美術館の「日本国宝展」には、展示替えがあるが135点の国宝が展示されている。
文化財保護法に基づき日本の国宝として保護されている国指定の文化財は1,144件あるというから、京都国立博物館の「日本の美のるつぼ」と奈良国立博物館の「超国宝展」の展示と合わせると、わが国の約25%の国宝が関西に集まっていることになる。
この機会を逃す手はない。一泊二日で3つの展覧会に足を運んだ。
まずは天王寺にある大阪市立美術館の「日本国宝展」。
大阪関西万博開催記念として、また、大阪市立美術館リニューアル記念特別展として開催されている。

展示は日本美術の巨匠たちの作品から始まる。
冒頭は雪舟の「天橋立図」。
室町時代(15~16世紀)の作品で京都国立博物館の所蔵。
それから、「唐獅子図屏風」。
右隻が桃山時代(16世紀)に狩野永徳が描き、左隻が江戸時代(17世紀)に狩野常信が描いたもの。皇居三の丸尚蔵館所蔵で以前見たことがある。
そして、尾形光琳の「燕子花図屏風」。
江戸時代(18世紀)に描かれたもので、根津美術館所蔵でこれも以前見たことがある。
さらに「伝源頼朝像」。京都神護寺が所蔵する三幅の絹本著色の肖像画で、「絹本著色伝源頼朝像、絹本著色伝平重盛像、絹本著色伝藤原光能像」を神護寺三像と呼ばれる。鎌倉時代(13世紀)のもの。
いずれも教科書で見たことがある国宝で、すでに見たことのある絵画もあるが、これらが一堂に会するのは奇跡的といえる。
絵画だけではなく、仏像などの展示も充実している。
たぶん興味のある方にはたまらないのだろう。
残念なのは、一度見てみたいと思っていた金印「漢委奴國王」。
展示期間がゴールデンウィークまでということで観ることができなかった。残念。
展示の入れ替えがあるので、すべての国宝が見られる、というわけではない。
例えば、長谷川等伯の「楓図」と長谷川久蔵の「桜図」も展示期間外。
でも、次の日に京都国立博物館を見たのちに、智積院に寄って法物館で実物と対面を果たした。
桃山時代(16世紀)に描かれた作品。
作者の長谷川等伯と久蔵については、安部龍太郎の小説「等伯」文春文庫で詳しく描かれている。ちなみに安部龍太郎はこの作品で直木賞を受賞した。
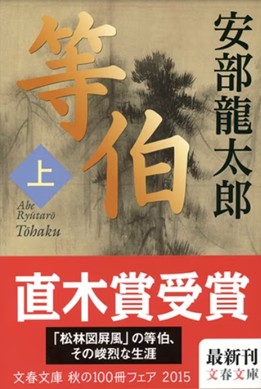
長谷川等伯の息子の久蔵が描いた「桜図」は、桜の花びらを胡粉で盛り上げて厚みを作っている。智積院の法物館で見た実物は心配になるほど劣化が激しい。よく京都から大阪まで移動させたものだと感心した。
大阪市立美術館と京都国立博物館で同時期に展覧館を開催しているのであるから、そのあたりの融通を聞かせれば、国宝を傷めるリスクを減らせることもできるのでは、と思うが。。。
「桜図」を完成させた久蔵は急死する。安倍龍太郎の小説「等伯」は、息子の久蔵を失った等伯が、その失意のなかで他人からの依頼ではなく自分自身にために描いたとされる「松林図屏風」を描くというストーリーを描いている。
長谷川等伯といえば「松林図屏風」。
東京国立博物館が所蔵する日本の水墨画の最高峰の国宝「松林図屏風」は、残念ながら今回の大阪、奈良、京都の国宝をめぐる展覧会には出品されていなかった。
今回の展覧会でこれだけの国宝を集めたことは素晴らしい。
でもそこには大人の事情もあり、必ずしも情熱だけでは理想どおりにはいかなかったのであろう。
開催にあたって苦労された方たちには頭が下がる。
そして、感謝しかない。
